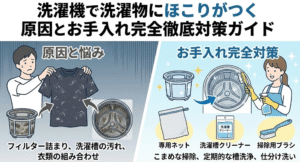新しい洗濯機の購入、おめでとうございます。しかし「自分で設置できるだろうか?」という不安はありませんか。
この記事は、そんなあなたのための完全ガイドです。洗濯機を自分で設置する作業は、ポイントさえ押さえれば決して難しくありません。
この記事を読めば、設置スペースや搬入経路の確認、蛇口や排水口の適合チェックといった必須の事前準備から、排水ホースや給水ホース、アース線の具体的な接続手順、さらには縦型とドラム式の違いや試運転の注意点まで、専門家が丁寧に解説します。
水漏れや騒音といった失敗を未然に防ぎ、安全かつ確実に設置を完了させるための知識がすべて手に入ります。
- 設置前に確認すべき5つの必須チェックリスト
- 水漏れを防ぐ排水・給水ホースの確実な接続方法
- 感電防止に不可欠なアース線の安全な取り付け手順
- 縦型とドラム式で異なる設置上の重要注意点
洗濯機を自分で設置する前の必須確認リスト
- 設置スペースと搬入経路の採寸は大丈夫?
- 蛇口の形状と高さは設置に適合してる?
- 排水口の位置と排水エルボの有無を確認
- 縦型とドラム式、設置方法の重要な違い
- 設置に必要な道具と別売り部品リスト
設置スペースと搬入経路の採寸は大丈夫?

洗濯機の設置で最も多い失敗は、購入後に「置けない」「通れない」と気づくことです。これを防ぐには、単に設置場所の寸法を測るだけでは不十分です。まず、洗濯機本体の寸法に加え、壁からの最低限の距離を確保する必要があります。メーカーは放熱やホースの取り回しのために、背面や側面に1.5cm以上、縦型洗濯機の場合はフタの開閉を考慮して上方に50cm以上の空間を推奨しています。ドラム式でも同様に、本体上方に十分な空間が必要です。
次に重要なのが「搬入経路」の確認です。玄関ドア、廊下の幅、階段の曲がり角など、洗濯機が通過するすべての箇所の幅と高さを測定してください。特にドラム式洗濯機は重量があるため、運搬する人の手や体を考慮し、本体サイズに最低でも10cmの余裕を持たせた経路幅が求められます。
最後に、設置場所そのものの環境も確認しましょう。床が平らで安定しているか、直射日光や高温多湿を避けられるか、といった点も重要です。不安定な場所や傾いた床は、運転中の激しい振動や騒音の原因となり、故障のリスクを高めます。これら「設置スペース」「搬入経路」「設置環境」の3点を事前にクリアにしておくことが、自分で設置を成功させるための第一歩です。
蛇口の形状と高さは設置に適合してる?

設置場所の次に確認すべき最重要ポイントが「蛇口」です。蛇口の形状や高さが洗濯機に適合していないと、取り付け自体が不可能になることもあります。これは洗濯機を購入する前に必ず確認すべき項目です。日本の家庭で一般的な蛇口は「万能ホーム水栓」や「洗濯機用ワンタッチ水栓」などですが、古い住宅では形状が異なる場合があります。
特に重要なのが蛇口の高さです。洗濯機の給水ホースは本体の上部に取り付けられるため、蛇口の位置が洗濯機本体の高さより低いと、物理的に干渉して設置できません。理想としては、洗濯機本体の高さよりも10cm以上高い位置に蛇口があることです。もし蛇口が低い場合は、「壁ピタ水栓」という部品に交換することで、蛇口の位置を10cm以上高くすることができます。これは専門業者に依頼せずとも、比較的簡単に自分で交換可能な場合が多いです。
また、蛇口の先端に給水ホースを接続するための「ニップル」という部品が必要になることもあります。最近の洗濯機には対応する部品が付属していることが多いですが、中古品を購入した場合や特殊な蛇口の場合は、別途ホームセンターなどで購入する必要があります。蛇口の確認は、単なる設置手順の一つではなく、設置プロジェクトそのものを左右する「関門」と捉え、慎重に確認してください。
排水口の位置と排水エルボの有無を確認

給水と同様に、排水環境の確認も不可欠です。まず、洗濯パン(防水パン)にある排水口に、「排水エルボ」というL字型の部品が取り付けられているかを確認してください。この部品は、排水ホースを確実に接続し、下水からの臭いや害虫の侵入を防ぐ「封水」という役割を担う、非常に重要なパーツです。もし排水エルボが見当たらない場合は、単にホースを差し込むだけでは不十分です。悪臭や水漏れの原因となるため、必ず管理会社や大家さんに連絡して設置してもらいましょう。
次に、排水口の位置です。排水口が洗濯機の左右や後方にあれば、付属のホースで問題なく接続できる場合がほとんどです。しかし、注意が必要なのは、排水口が洗濯機の真下に来る「真下排水」のケースです。この場合、通常のホースでは接続できず、多くの場合、メーカー指定の「真下排水キット」という別売りの部品が必要になります。
真下排水は、設置スペースを有効活用できるメリットがある一方、一度設置すると排水口へのアクセスが極めて困難になるという大きなデメリットがあります。排水口は定期的な掃除が必要な場所ですが、真下排水では洗濯機を動かさない限り掃除ができません。これが原因で詰まりや悪臭が発生するリスクも高まります。ご自宅の排水口の位置を正確に把握し、必要であれば適切な部品を事前に準備しておくことが、長期的な快適さを保つ鍵となります。
縦型とドラム式、設置方法の重要な違い

洗濯機のタイプによって、設置の難易度や注意点が大きく異なります。特に「縦型」と「ドラム式」では、その違いを理解しておくことが極めて重要です。まず最も大きな違いは「重量」です。一般的な縦型洗濯機が30kgから40kg程度であるのに対し、ドラム式は80kg以上と非常に重く、成人男性2人以上での運搬が必須です。一人での設置は怪我や家屋の損傷に繋がるため、絶対に避けてください。
次に、ドラム式洗濯機に特有の重要な作業が「輸送用ボルト」の取り外しです。輸送中の振動で内部のドラムが破損しないよう、ドラム式洗濯機は数本のボルトでドラムが固定された状態で出荷されます。設置後、運転前にこのボルトを必ず取り外さなければなりません。もしボルトを付けたまま運転すると、モーターの力が逃げ場を失い、本体が激しく揺れたり、大きな音を立てたりして、最悪の場合は即座に故障します。
また、設置スペースの考え方も異なります。縦型は上部のフタを開けるための垂直方向のスペースが必要ですが、ドラム式は前面のドアを開けるための水平方向のスペースが必要です。壁や収納棚にドアがぶつからないか、ドアを開けた状態で人が通れるか、といった動線も考慮して設置場所を決める必要があります。これらの違いをまとめた以下の表を参考に、ご自身の状況に合った洗濯機を選び、適切な設置計画を立ててください。
| 特徴 | 縦型洗濯機 | ドラム式洗濯機 |
| 重量 | 比較的軽い (約30~40kg) | 非常に重い (約80kg以上) |
| 運搬 | 1~2人で対応可能 | 2人以上が必須 |
| 輸送用ボルト | なし | 運転前に必ず取り外す必要あり |
| ドアの空間 | 上方向への開閉スペースが必要 | 前方向への開閉スペースが必要 |
| 設置の複雑さ | 比較的シンプル | 重量とボルトのため複雑 |
設置に必要な道具と別売り部品リスト
洗濯機の設置をスムーズに進めるためには、事前の道具の準備が欠かせません。作業を始めてから「あれがない、これがない」と中断し、ホームセンターに走るような事態を避けるため、あらかじめ必要なものを揃えておきましょう。基本的な工具と、状況に応じて必要になる可能性のある部品をリストアップしました。
まず、ほとんどの設置作業で必要になるのが基本的な工具です。アース線のカバーを開けたり、ホースクリップを締めたりするために、プラスとマイナスのドライバーは必須です。固く締まった接続部を緩めるために、プライヤーやレンチがあると安心です。また、給水・排水ホースを取り外す際に内部に残った水がこぼれることがあるため、雑巾やタオルを数枚用意しておくと床を濡らさずに済みます。
さらに、設置環境によっては特殊な部品が必要になります。蛇口が古いタイプの場合は「ニップル(水栓つぎて)」、蛇口の位置が低い場合は「壁ピタ水栓」が必要です。排水口が洗濯機の真下にある場合は「真下排水キット」が欠かせません。これらはすべて別売りなので、事前に自宅の環境を確認し、必要であれば洗濯機本体と一緒に購入しておきましょう。また、排水ホースの接続をより確実にするために、防水用のビニールテープと結束バンドを用意することを強く推奨します。これらは安価で手に入り、水漏れリスクを大幅に低減できます。
| 分類 | 品目 | 主な用途 |
| 必須工具 | プラスドライバー | ホースクリップ、アース線カバーのネジ |
| マイナスドライバー | アース線カバーをこじ開ける際など | |
| プライヤー/レンチ | 固い接続部、ナットの締め付け | |
| タオル/雑巾 | 作業中の水漏れ受け | |
| 推奨品 | 防水ビニールテープ | 排水ホース接続部の補強 |
| 結束バンド | 排水ホースの抜け防止 | |
| 状況別部品 | ニップル(水栓つぎて) | 古い形状の蛇口への接続 |
| 壁ピタ水栓 | 蛇口の位置が低すぎる場合 | |
| 真下排水キット | 排水口が洗濯機の真下にある場合 | |
| 防振ゴム・マット | 振動や騒音の軽減 |
初心者でも安心!洗濯機を自分で設置する手順
- ステップ1:排水ホースを確実に取り付ける
- ステップ2:給水ホースを水漏れなく接続する
- ステップ3:アース線と電源プラグを安全に接続
- 最終チェック:水平設置と試運転のポイント
- 古い洗濯機の正しい処分方法(家電リサイクル法)
ステップ1:排水ホースを確実に取り付ける

すべての準備が整ったら、いよいよ設置作業に入ります。手順は「排水」「給水」「電気」の順に進めるのが安全で効率的です。最初のステップは、水漏れ事故の最大の原因となる「排水ホース」の接続です。ここでの少しの手間が、将来の大きなトラブルを防ぎます。
まず、排水ホースを洗濯機本体の排水口に差し込み、「ホースクリップ」でしっかりと固定します。クリップが緩んでいると、排水時の水圧でホースが抜けてしまう可能性があるため、ドライバーなどを使って確実に締めてください。次に、ホースのもう一方の端を、床の排水口にある「排水エルボ」に接続します。
この排水エルボとの接続こそが、最も重要なポイントです。単に差し込むだけでは不十分です。ホースをエルボに差し込んだ後、まず付属のホースクリップで固定します。次に、その接続部分の上から防水用のビニールテープを隙間なく何重にも巻き付けます。最後に、テープの上から結束バンドをきつく締めて、物理的にホースが抜けないように補強します。この「クリップ・テープ・結束バンド」の三重の対策により、接続は盤石になります。
ホースの取り回しにも注意が必要です。ホースが途中で折れ曲がったり、家具の下敷きになったりしないようにしてください。また、排水をスムーズにするため、ホースの途中が排水口より10cm以上高くならないように配線しましょう。
ステップ2:給水ホースを水漏れなく接続する
排水ホースの設置が完了したら、次は給水ホースの接続です。こちらは水道の圧力が常にかかる部分なので、じわじわとした水漏れが起こりやすい箇所です。作業は慎重に行いましょう。
まず、給水ホースを接続する前に、ホースの両端にある接続部分の内部を覗き込み、「ゴムパッキン」の状態を確認してください。このパッキンにひび割れがあったり、硬化していたりすると、水漏れの直接的な原因になります。もし劣化が見られるようであれば、無理せず新しい給水ホースに交換することをお勧めします。パッキンは消耗品であるという認識が重要です。
接続は、蛇口側から先に行うのが一般的です。最近の洗濯機用蛇口やホースは、ワンタッチでカチッと接続できるタイプが多く、取り付けは簡単です。接続部を蛇口にしっかりと押し込み、ロックがかかるのを確認します。次に、洗濯機本体側の給水口にホースを接続します。こちらはネジ式になっていることが多く、手で回して締め付けます。
この時、斜めにねじ込まないように注意し、最初は手で軽く回し、まっすぐ入っていることを確認してから、最後にプライヤーなどで軽く増し締めします。プラスチック製の部品が多いため、力を入れすぎて締め付けると、ネジ山が破損して逆に水漏れの原因になるので注意してください。
ステップ3:アース線と電源プラグを安全に接続
水回りの接続が完了したら、最後に電気系統の接続です。安全のために、必ず「アース線」を接続してから「電源プラグ」を差し込む、という順番を厳守してください。
アース線は、万が一洗濯機が漏電した際に、電気を地面に逃がして感電事故を防ぐための命綱です。洗濯機は水と電気を同時に使うため、他の家電製品よりもアース線の接続が極めて重要になります。コンセントの下側にあるアース線接続端子に、洗濯機から出ている緑と黄色の線を接続します。接続端子には、ネジを緩めて挟み込むタイプと、フタを開けて差し込むだけのワンタッチタイプがあります。どちらのタイプでも、銅線部分が確実に金属部分に接触するように、しっかりと接続してください。
ここで絶対に守るべき注意点があります。アース線は、ガス管、電話線、水道管、避雷針には絶対に接続してはいけません。法律で禁止されており、火災や感電の重大な事故につながる危険があります。
アース線の接続が完了したら、最後に電源プラグをコンセントに差し込みます。この際、手が濡れていないことを必ず確認してください。また、洗濯機は消費電力が大きいため、延長コードを使わず、壁のコンセントに単独で接続するのが原則です。
最終チェック:水平設置と試運転のポイント

すべての接続が完了したら、最後の仕上げとして「水平設置」と「試運転」を行います。この最終チェックを怠ると、騒音や故障、水漏れの原因を見逃すことになります。
まず、洗濯機が水平に設置されているかを確認します。本体の上部四隅を対角線上に軽く押してみて、ガタつきがないか調べます。もしガタつく場合は、本体下部にある調整脚を回して高さを調整し、4本の脚がすべて均等に床に接地するようにします。洗濯機が傾いていると、脱水時に異常な振動や騒音が発生し、内部の部品に大きな負担がかかります。
水平が確認できたら、いよいよ試運転です。洗濯物は入れずに、蛇口をゆっくりと全開にします。その後、洗濯機の電源を入れ、「洗い」や「すすぎ」のみの短いコースを選択してスタートさせます。運転が始まったら、給水ホースの蛇口側と洗濯機側の接続部、排水ホースと排水エルボの接続部、排水口の周りなどを注意深く観察し、水滴が一滴でも漏れていないかを確認します。脱水が始まったら、異常な音や大きな振動がないか耳を澄ませてください。この試運転で問題がなければ、設置作業は無事完了です。
古い洗濯機の正しい処分方法(家電リサイクル法)
新しい洗濯機の設置が無事に終わると、古い洗濯機の処分という最後の課題が残ります。洗濯機は「家電リサイクル法」の対象品目であり、自治体の粗大ゴミとして出すことはできません。法律に基づいた適切な方法で処分する義務があります。
主な処分方法は3つあります。最も簡単なのは、新しい洗濯機を購入した販売店に引き取りを依頼する方法です。配送時に同時に古いものを回収してくれます。この場合、「リサイクル料金」と「収集運搬料金」を販売店に支払います。
購入した店が不明な場合や、引っ越しなどで依頼できない場合は、お住まいの自治体が案内する「家電リサイクル受付センター」に連絡し、収集を依頼します。この場合も、リサイクル料金と収集運搬料金が必要になります。
費用を最も抑えたい場合は、自分で「指定引取場所」という回収拠点まで運ぶ方法です。この場合、収集運搬料金はかからず、リサイクル料金のみで済みます。ただし、この方法と受付センターに依頼する方法では、事前に郵便局で「家電リサイクル券」を購入し、リサイクル料金を支払っておく必要があります。
料金の目安として、洗濯機のリサイクル料金は2,530円から、収集運搬料金は業者によって異なりますが、数千円程度が一般的です。不法投棄は罰則の対象となるため、必ずこれらの正規のルートで正しく処分してください。
総括:洗濯機を自分で設置する作業は正しい知識と準備で成功する
この記事のまとめです。
- 洗濯機の自己設置は、正しい手順と事前確認を行えば可能である。
- 設置の成否は、作業前の準備段階でほぼ決まる。
- 設置スペースは、本体寸法だけでなく、壁からの放熱・作業スペースも考慮する。
- 搬入経路は、本体幅に最低10cmの余裕を見て計測することが重要である。
- 蛇口の高さが洗濯機本体より低い場合、設置は不可能であり、「壁ピタ水栓」への交換が必要となる。
- 排水口には「排水エルボ」が必須であり、下水の臭気や害虫の侵入を防ぐ役割を持つ。
- 排水口が洗濯機の真下にある「真下排水」は、別売りの専用キットが必要となる。
- ドラム式洗濯機は非常に重く、2人以上での運搬が絶対条件である。
- ドラム式洗濯機の「輸送用ボルト」は、運転前に必ず取り外さなければ故障の原因となる。
- 排水ホースの接続は、クリップ、防水テープ、結束バンドの三重固定が水漏れ防止に有効である。
- 給水ホース接続前には、内部のゴムパッキンの劣化を確認することが重要である。
- アース線は感電防止の安全装置であり、電源プラグより先に接続する。
- アース線をガス管や水道管に接続することは、法律で固く禁じられている。
- 設置後は必ず水平を確認し、ガタつきがあれば調整脚で修正する。
- 最終確認として、洗濯物を入れずに試運転を行い、水漏れや異常音がないかを確認する。
- 古い洗濯機は家電リサイクル法に基づき、料金を支払って正しく処分する義務がある。